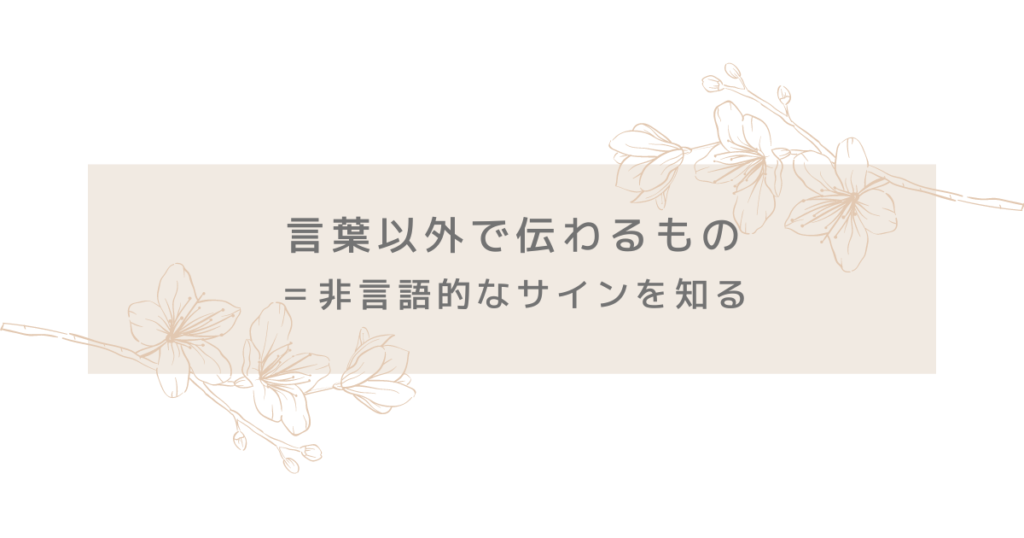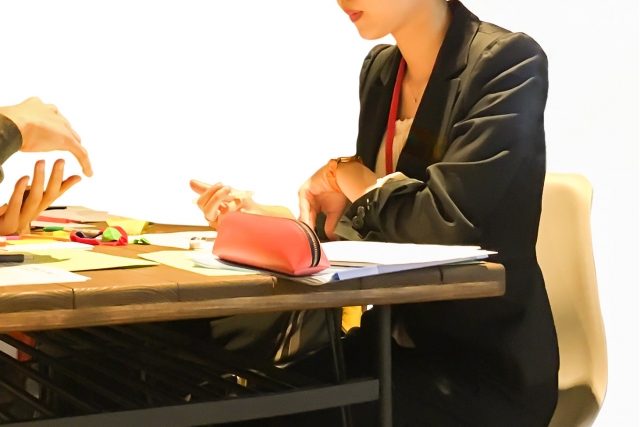コーチングの会話では、クライアントの言葉だけでなく、背後にある課題や障害なども聞き取る、感じるとる必要があります。
通常の会話では、人は無意識のうちに、自分にとって都合の良い結論を出そうとし、話し手の情報に基づいて、主観的に解釈してしまいがちです。
会話の内容の中では、結論や解釈がすでに聞き手側の頭の中で都合よく処理されているため、話し手が価値ある情報を話したとしても、実際にはそれを聞いていないということもたびたび起こり得ます。
このように、話し手と聞き手が同じことを話していながらも、まるで異なる解釈の中で、会話が進んでいくケースは多く、つまりミス・コミュニケーションが常に発生しているわけです。
通常の会話でも、双方の解釈の違いが生じてしまいがちなため、お互いのずれをなくすポイントが重要です。これにより、クライアントの盲点や見落とし、メッセージの深層を聞きとることができます。
1、相手の話を聞きとるための10のポイント
相手の話を聴き取るためには、できるだけ多くの種類の視点を持っておいた方がいいですよね。
人にはそれぞれ、情報の処理方法や物事を決断するパターンがあります。
ですから、コーチはクライアントがどのようなものの捉え方をする傾向があるのか、クライアントの判断のパターンは何か、どのような前提を持って人と関わっているのか、など注意深く聞くことで、コーチングが創造的で深みのあるものになります。
ここでは、相手の話を聞きとるための12のポイントをご紹介いたしますので、それらを参考にして相手の話を聞いてみてください。
-
- 姿勢…相手の態度、取り組みの姿勢を理解する
相手が良く使い繰り返している言葉に注意を払い聞く。ある特有の言葉は、相手の態度や取り組み姿勢を理解するための手がかりとなります。
「どの言葉、フレーズがよく使われているのだろう?」
「それはどんな姿勢の表れなのだろうか?」 - 一貫性…相手の話の内容は、つじつまがあったものなのかを観る
相手の会話の中にある振る舞いや感情を聞きとり、言葉の意味と声のトーン、調子、速さ、行動などから、本心と一致しているかどうか、一貫性があるのかどうかを確認します。
「言葉と本音は一致しているだろうか?」
「会話の内容に一貫性はあるだろうか?」 - 差し迫った必要性…クライアントのニーズを聞き取る
ニーズは、人が充足するために必要なものですから、ニーズが満たされていないと、それを手に入れるためにあらゆる振る舞いをします。相手にとって差し迫った必要性は何か、を追究して本人に気づきを与えます。
- 価値観…相手にとって生きていく中で一番大切にしているもの
何かを決断をするとき、自分自身の大切にしているルール、価値観に近いものを選択しようとします。価値観を見極めるために質問をしていきます。することです。すればよいのです。
「あなたが生きている中で大事にしているなことは何ですか?」
「あなたにもこれだけは絶対に許せないことがあると思います。それは何ですか?」 - 強み…相手にとって真の強み
誰かの話を聞くうちに、その人の特徴などを聞きとることができます。相手が自覚している強みもその一つです。コーチがしてあげるのは、相手は無意識に当たり前に行っているだけなのに周りから褒められたり、感謝されたりすることです。それこそ真の強みになります。 - 動機…相手の動機は?
何が人を動かすのでしょうか?動機づけには積極的なものもありますし、ときに、否定的、消極的な動機から行動することもあります。いずれの場合も、クライアントがどのような動機を持っているのかをよく聞きとり、そして、聞きとったままの真実を相手に伝えてあげましょう。 - 文化的背景…文化の違いを知り、受け止める
相手は、働いている場所の文化はどのようなもので、どのように馴染んでいるのでしょうか、また、どのような家族構成でどのような文化が存在し、どのような影響をうけているのでしょうか? それらの違いを確認して知ることと、それをきちんと受け止めてあげることです。 - 言葉以外のメッセージ…相手が感じていることでまだ言葉にできていないもの
語られていないことの中から、相手の状況を知らされることがあります。本人もまだ気がついていないこと、相手が感じていることでまだ言葉にできていない領域、それらをコーチが言葉にしてあげたときに、相手に気づきを与えることができます。 - 話す調子…話す調子は感情そのもの
相手が話す内容だけでなく、話す調子にも注目します。楽しいそう、疲れていそう、気乗りしていなさそう、不機嫌そう、言葉の意味は相手がその言葉に込める感情によって変わってきます。 - シナリオ…相手の意図
会話の中から、相手には、どのようなシナリオ(筋書き)があるかを予測します。
・どんな物語があるように感じますか?どのような意図を観じますか?
・未来はどのようにイメージされているのでしょうか?
- 姿勢…相手の態度、取り組みの姿勢を理解する
2、相手のものごとの捉え方を聞き分ける
ものごとの捉え方や考え方を観察することによって、クライアントに対して、より効果的な質問や提案をしていくためのものです。
いくつかご紹介いたします。
① 視点を変える
私たちは、事実そのものが直接自分に影響しているわけではなく、その事実に対して自分が意味付けを加えて、さまざまな感情や思いを抱いているのです。
ですから、起こった事実は変わらないですが、意味付けを変えることはいくらでも可能なのです。
- 店員のの態度が傲慢で、不快に思うし、頭にきた
- 上司が理不尽な指示をしてくるので、仕事に対する意欲がなくなる
- 自分にはどうも能力がないようなので、仕事がうまくいかない
問題・課題に遭遇すると、私たちは、相手を変えるか、自分を変えるかの選択を迫ります。
そして、たいていそれはあまりいい結果に至りません。
第三の選択として、「視点を変える」というスタンスを持つのです。
相手も変えない、自分も変えない、しかし視点を変える。
それによって行動が断然やりやすくなるはずです。
こちらの記事もおすすめです↓

② 1つの出来事を5段階で捉える
例えば、「英語のテストでなかなか良い結果がでない」という事実は、以下の5段階のレベルで捉えることができます。
- アイデンティティ(自己認識)
「私は頭が悪い、だから英語のテストで悪い点をとってしまう」 - ビリーフ(信念)
「うちの家族はみんな英語がきらいといっている。きっとその遺伝がある」 - 能力
「私は英語を覚える能力がないので、悪い点をとった」 - 行動
「英語の勉強の仕方が悪かったからテストができなかった」 - 環境
「英語の先生の教え方が良くない。それが原因だ」
この5段階の①の「アイデンティティ」は「私」そのものになります。
これを否定的に捉えてしまうと自己否定になってしまいますから、決してここを否定しないでください。
仮に、④の「行動」のレベルで捉えれるのであれば、英語の勉強方法という行動さえ変えればなんとかなるというものなので、③の「能力」や、①の「アイデンティティ」は否定されません。
否定的なものごとは、より下の位置にある④や⑤に近いレベルで認識してみると、無理に思い詰めることが少なくなっていきます。
思い詰めやすい人は、上の位置の①や②を否定してしまい自己否定をしてしまっているのです。
ここでは「事実」が重要なポイントなのではなく、それを①から⑤のどのレベルで捉えているのかを認識することがとても重要なのです。
①に近い捉え方をすれば、当然行動は抑制されます。
①、②、③のレベルにいるときに、④のレベルに移動することができれば、行動を起こしやすくなるでしょう。
逆に肯定的な出来事をより①のレベルで捉えると、自己肯定感が高まります。
例えば、相手を褒めるときや仕事で成功したときには、⑤の「環境」のレベルで捉えるのではなく、「あなたは天才だ!」「自分は天才だ!」と、うまくいっていることを「アイデンティティ」のレベルで捉えるのです。
逆に、相手を注意するときはその反対に、行動レベルを指摘してあげると良いでしょう。
こちらの記事もおすすめです↓

③ 内的基準型と外的基準型
「内的基準型」と「外的基準型」を簡単に説明しますと、物事に対する判断や決定を下すとき、「内的基準型」は判断基準を自分の中に求め、「外的基準型」は判断基準を外に求めます。
このように、人は大きく2つのタイプに分かれます。
内的基準型の場合、基準は内側にあり、自分の基準、自分の正しさに基づいて物事を決断しますから、決断のスピードが速く、スマートに見えます。しかし、いきすぎると、独善的で頑固になります。
外的基準型の場合は、内的基準型の反対で、基準は外側にあり、人の考えや評価、常識や慣習を重んじます。
外の意見を聞いていって最後は自分が決める、自分の意見を最初に持ちつつ周囲の反応で決めるなど、タイプにはいくつかのバリエーションがあるようです。
④ 直進型と回避型
動機づけ方法に関して、直進型と回避型という2種類のタイプをご紹介します。
直進型とは、「ほしいものに向かって逃げずに真っすぐ進んでいく」というスタイルです。
たとえば、問題・課題が発生して仕事で困難なことが起きたときに、成功するように真正面から向き合い正面突破を図っていくというスタイルです。
一方、回避型とは、問題・課題が発生したとき、失敗しないようにそれらを回避するための方法を探していくというスタイルになります。例えば、「人に直接言うのはいやだし、だからといって、黙っているのもいやだから、誰かにかわりに言ってもらう」という具合です。
回避型の場合、ほしいものを選ぶときは消去法をとりやすく、直進型の場合は、まさに好きなものを直接とりにいきやすくなります。
仕事を任されたとき、「・・・がうまくいくこと」「・・・が成功すること」と語るなら直進型で、「失敗しないように」「・・・にならないようにすること」なら回避型になります。
どちらかのほうが良い悪いとかではなく、バランスよく配置するとベストですよね。
⑤ 判断をパターン化する表現
- 一般化
「みんな」「誰でも」「いつでも」といった表現に代表されます。「みんな」とか「誰でも」とか、言葉のうえでお互いに了解してしまっていますが、「みんながそう言っている」と言いたくなります。「みんな」と聞いたら「それは誰のこと?」と聞き返すと、そのパターンに自動的にはまらずにすみます。
「みんなが言っているっていうけど、誰と誰が言っているの?」
「ふつうって、どういう基準なの?」
これらの質問をすることで、現実を具体的にすることができます。 - レッテル
レッテルとは、行動や一連の過程が固定的なものとして扱われることを指します。たとえば、1度しか失敗したことがないだけなのに、彼は仕事のできない人と思われてしまうことです。
例えば、「あいつは不良だ」「彼は不真面目」「あの人は信用できない」など、レッテルを貼ることによってできあがってしまっている固定観念に対しては、名詞のもとになった一連の行動やプロセスを、その過程を表す表現に戻すような質問が有効です。
●仕事ができない人 → どんな仕事をどのように行動されたのですか?
●信用できない人 → どんな事実があったのですか?
●不良だ → 何をしたのですか? - 思い込み
「自分は嫌われている」「どうせ言っても聞いてもらえない」「人は変われない」「みんな自分のことしか考えていない」「友情なんてない」・・・このように今、思ったとしたら、それは事実ではないかもしれません。それは、相手に確認すればすぐに答えが出るのです。
自分の思い込みに注意して、思い込みに気がついたときには、それを解除するためのいくつかの効果的な質問をすることです。
●どうしてそうだということが分かったの?
こちらの記事もおすすめです↓

まとめ
相手の話を聞きとるためには、自分なりのリスニング・チャートを持つことと、話を聞きとるエクササイズを繰り返し行い、会話を熟達させます。
さらに、クライアントの情報処理方法や判断パターンを理解し、異なる捉え方を試す質問をすることで、クライアントに新たな選択肢を提供します。
注意深く聞くことで、コーチングが創造的かつ深いものになります。